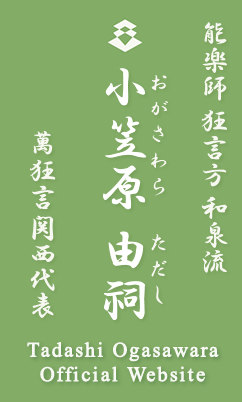野村万蔵家を母体とする 「萬狂言」 関西代表 小笠原由祠 (能楽師 和泉流狂言方)のホームページです。
(運営:アトリエ オガ.)

■ 仮面喜劇の源流を求めて
―狂言とコンメディア・デッラルテの根底にあるもの―
論文 : 桃山学院大学にて発表 (2015年3月)
はじめに ― 共同研究の目的と活動
桃山学院大学共同研究(地域連携)「中近世の日本とイタリアにおける仮面喜劇の生成発展と現代的実践について」(2012-2014年度)では、狂言とコンメディア・デッラルテの比較研究を通じて、仮面喜劇の普遍的な源流を探ることに取り組んできた。
日本とヨーロッパの歴史には、多くの点で興味深い符合が見られる。中近世における仮面喜劇の生成発展もそのひとつである。すなわち、日本の狂言とイタリアやフランスで隆盛をみたコンメディア・デッラルテがそれである。両者の比較研究は、過去にも18世紀イタリアの喜劇作家ゴルドーニを軸として行なわれたことがあるが1)、本プロジェクトは、次の2点において、従来日本でもイタリアでも全く見られなかった視点にもとづいている。
まず、コンメディア・デッラルテの全盛期である近世後期よりもむしろ、その成立期にあたる中世末期から近世初期のイタリアに注目し、同様に中世末期に成立した狂言との文化史的な比較を試みる点である。第二に、現代において狂言およびコンメディア・デッラルテの上演と両者のコラボレーションを行なっている役者と演出家の参加により、両者が持つ本源的かつ普遍的な文化的価値を実践面から探ろうとする点である。さらに、これらの作業を通して、多様な劇作的要素が社会にもたらす影響についても検証し、それをふまえた新しい演劇のありかたを追究していきたいと考えている。
プロジェクトのメンバーである和泉流狂言師の小笠原匡は、本プロジェクト発足以前の2006年より、「Eenen延年」と題する一連の企画に取り組んでいる。この題は、言うまでもなく、狂言の成立以前から存在していた芸能である延年に因んでいる。延年は特定の芸能形態というよりもむしろ、舞楽や散楽など多様なジャンルの芸能が行なわれる機会を意味し、能・狂言の母体ともなった猿楽とも深いかかわりを持つと考えられている2)。小笠原はまた、この取り組みの一環として、同じく本共同研究プロジェクトのメンバーである演出家の多木陽介、俳優のアンジェロ・クロッティAngelo Crottiおよびアンドレア・ブルニェーラAndrea Brugneraとともに、狂言とコンメディア・デッラルテを融合した演劇を2009年と2011年に上演していた3)。それは、各々一個のジャンルとして確立した狂言とコンメディア・デッラルテの単なる協演4)ではなく、両者に通底する根源的要素を探り、芸能というものが本来有していた原始的なダイナミズムを現代に取り戻そうとする意欲的な試みである。
本プロジェクトは、この4名と桃山学院大学教員およびヴェネツィア・カ・フォスカリ大学の日本学教員が協力することにより、「Eenen延年」の取り組みを学術的側面からも掘り下げることを目指して活動してきた。2012年9月には、第6回「Eenen延年」企画としての「黒い媼の舞」「うもうて死ねる」「健康元年」の公演5)に合わせたシンポジウム「狂言とコンメディア・デッラルテの出会う所6)」、同10月には、ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学におけるワークショップ、講演、デモンストレーション、シンポジウム「Alla ricerca delle radici del Kyōgen e della Commedia dell’Arte(狂言とコンメディア・デッラルテの源流をさぐる)7)」、2014年3月には、同大学におけるワークショップ、講演、デモンストレーション、シンポジウム「Sciamano, buffone, satira ― Origine e forma attuale del Kyōgen, teatro comico tradizionale giapponese(シャーマン、道化、風刺 ― 日本の伝統喜劇、狂言の源流と現在の姿)8)」、同年10月には、ボローニャ大学との合同企画によるワークショップ、講演、デモンストレーション、シンポジウム「Riprogettare il Kyōgen tra tradizione e creativita(伝統と創造性の間で狂言を再創造する)9)」を開催し、2015年2月にも同様の一連の催しを計画している10)。
本稿は、これまでの活動でわれわれが明らかにしてきた内容を、日本の立場から小笠原が、イタリアの立場から和栗がまとめたものとなる。
1. 日本の立場から
(1) 「延年プロジェクト」について
狂言の源流を探るため2006年に立ちあげた「延年プロジェクト」は、2009年より、演出家多木陽介氏、イタリア人俳優アンジェロ・クロッティ氏、イタリア人俳優アンドレア・ブルニェーラ氏と共に、イタリアの仮面劇コンメディア・デッラルテとのコラボレーションを始め、2012年からは桃山学院大学共同研究プロジェクトとも連携して活動を展開してきた。
このプロジェクトの主な目的は、650年間もの長い年月をかけて伝承され洗練されてきた様式美から離れて、社会風刺性を色濃く持った発生当初の狂言の再現を試みることにある。すなわち、狂言台本の中にある社会風刺性を鮮明にするため、その内容を大きく書き換えると同時に、狂言の技術・様式を一切用いない代わりに、コンメディア・デッラルテの様式を借りての翻案上演をするというものである。コンメディア・デッラルテとのコラボレーションを行なう理由は、後述するように、強烈な社会風刺性を持つなど、狂言発生時の演技形態に近いと考えられるからである。これは、喜劇としての狂言のオリジナルな姿を探求するための取り組みであったが、それを通して、狂言という芸能、狂言師と言う存在を考える上で、さらに重要な側面が見えて来た。
延年は平安朝にて盛んに執り行われた仏教儀礼であり、また様々な当時の芸能が一堂に会する日本で最初の芸能祭でもあった。「延年プロジェクト」は、和泉流狂言師・小笠原匡が、伝統芸能との狂言コラボレーションや、現在途絶えてしまった様々な芸能を現代風にリメイクすることにより、延年を現代の芸能祭「Eenen延年」として、復活させる試みとして始めた。
門閥外で狂言の世界に足を踏み入れた私(小笠原匡)は、子供の頃より理屈抜きで身体に叩きこまれている所謂サラブレッドとは当然同じではなく、師よりの教えを受ける度毎に、なぜ斯様な表現をするのか、どのようにしてこの様式が創られたのか、と考えていた。それが転じて“日本芸能のルーツを見つけたい”と考えるに至ったのである。
初回は出雲の阿国に焦点を当て、平成版「阿国歌舞伎」として復活させ11)、第2回は平家琵琶と狂言を融合させた「延年版・平家物語」を上演し12)、第3回は「ユネスコ世界無形文化遺産」に認定された世界に誇る日本文化・芸能「能楽・狂言と文楽を融合した新作「狂言文楽浪花話」を作り上げ上演した13)。
しかし、日本の他ジャンルとコラボレーションしていくうちに、なぜ狂言が現在のような劇形態を持つに至ったのかを探りたいという新たな気持ちが湧き起こり、第4回からは、狂言の源流を探っていくことにした。そのためには、日本の外から見つめ直すことが必要であると考え、他の日本芸能ではなく、類似点が大変多いイタリア伝統仮面劇コンメディア・デッラルテと新たな手法でのコラボレーションを始めたのである。
昨今、「コラボレーション」と銘を打った企画が多数催されているが、一口にコラボレーションと申しても、その内容、あり方は様々である。狂言と他の伝統芸能のコラボレーションにおいては、それらを比較上演することにより、それぞれの芸能が持つ様式性を通して、狂言の魅力を新たに見出すことが主な目的であった。しかし、従来の試みでは、互いの芸能要素を切り張りしているだけのものや、共通のテーマにもとづきそれぞれの芸能がオムニバス上演したに留まるものが大半であった。
そこでわれわれは、長い年月をかけて伝承され洗練した様式美から離れて、社会風刺性を色濃く持った発生当初の姿の狂言の再現を試みるため、狂言台本の中にある社会風刺性をもとに、その内容を大きく書き換え、コンメディア・デッラルテの技術・様式によって上演することにしたのである。台本は主に私が手掛け、演出はイタリアから来日したクロッティ氏と多木氏にお願いした。
三者相談の結果、「鎌腹」・「蚊相撲」という狂言の代表曲をもとに、それぞれを「はらきらず」・「異人相撲発気揚々」と題し、日本が伝統や文化を失う発端ともなった時代の滑稽な様を風刺する内容にし、明治文明開化期の江戸に時代設定して書き下ろした。
これらの作品では、登場人物が用いる言語にもこだわった。すなわち、上方言葉のほかに、現在ではほとんど耳にしなくなってしまった江戸弁や千葉弁、廓言葉を用いることにより、その言語の音やリズムの面白さを通してキャラクターを表現する要素としたのである。多様な地方の言語が入り混じる舞台というのは、まさにコンメディア・デッラルテの特徴でもあった14)。
この公演は、「延年プロジェクト」での新たな取り組みの幕開けとなった。
(2) 狂言形成の時代背景
狂言は、日本が世界に誇る芸術文化のひとつであり、能と合わせて世界ユネスコ無形文化遺産として日本で最初に認定を受けたものである。中世にはおおよそ現在の形で成立していたといわれており、室町時代にジャンルとして確立した。以後650年間、一度も途絶えることなく現在まで伝承されているという点で、世界に類を見ない演劇である。
中世(鎌倉・室町時代)とは、古代(飛鳥・奈良・平安時代)より脈脈と続いていた天皇・公家など貴族中心の律令制が事実上崩壊し、元々は貴族の下人であった武家が台頭を始める、大きな社会変革の時代であった。しかし、武家中心の安定した政権である幕藩体制が確立するのは近世(江戸時代)であり、中世には、依然として影響力のあった皇族・公家と、新興勢力の武家が、弱者である民衆を巻き込み、絶え間ない争いによる喧噪が繰り返えされていた。人々は常に生死と向き合い、明日無い我が身を嘆きながらも、前向きに今を精一杯生きようという、新しい仏教観や価値観が様々生まれてきた。いっぽう、一揆など物情騒然たる中で、様々な豪華な建物が造営され、戦乱の最中に茶道・花道など様々な文化が成立したカオス的な世の中でもあった。その中で誕生したのが、当時「猿楽」と呼ばれていた狂言と能なのである。
「猿楽」は、古代に仏教伝来と共に大陸より伝わった「散楽」という庶民的曲芸が、日本古来の神楽などと接合し転化したもので、元々は滑稽な物真似芸であったが、やがて狂言と能という二つの演劇形態を生みだした。狂言と能は、それぞれに役割を分担し、表現する題材・情趣・世界観を分け合った。
能は、本説である出典や典拠を重視し、『源氏物語』『平家物語』など、主に貴族社会を描き、演技も求心的、象徴的で重厚である。それに対して狂言は、庶民の日常生活において笑いを誘う断面を切り取って舞台化したものである。登場人物も身分の低い階級が中心であり、それらを開放的、具象的に描いている。狂言と能は劇構成・技法様式は共通しているが、現実認識・仏教観などは非常に異なるので、よく双子の関係に例えられる。
古来より「笑う門には福来る」と言うように、笑いには祝言性があり、言葉遊びや面白おかしい所作で人々を笑わす伝統的滑稽技は古くから存在していた。初期の「猿楽」も物真似中心の滑稽芸であった。しかし、「笑い」は社会構造や価値観の変化に左右されやすく、なかなか寿命を長く保つ事が出来ない。多くは特定範囲だけに通じて、ある場面を笑う人もいれば、逆に不愉快になる人もいる。また、「笑い」には常に意外性が必要で、繰り返すことにより飽きられてしまう。広範囲の人々を笑わせ、時代を乗り越え維持することは容易ならざるのである。狂言がこの困難を克服したのは、言葉遊びや滑稽な身振りだけでなく、普遍的内容の物語性を持ったからであろう。
狂言の代表的な登場人物である太郎冠者は、小回りが利くが臆病、酒に目がなくお人好し、底抜けに明るい、といった非常に庶民的な人間像であり、特定の個性を持つ人間ではなく、類型化された人物像として描かれている。また、劇中の主従関係は、日常社会の上司と部下の雇用関係や、親子の上下関係など、時代や場所を越えたいかなる場面にも置換可能であり、その人間関係が織り成す笑いが普遍的要素を兼ね備えているのである。
近世になると、狂言は能とともに武家式楽となり、役者たちは諸藩大名に召抱えられた。これにより、役者たちの経済的不安が解消されたが、狂言はそれと引き換えに庶民性を失うことになった。保護者である武家を直接的に批判したり揶揄したりすることは許されなかったからである。しかし庇護を受けたお陰で芸術性を高めることが可能になり、セリフに複合的意味を持たせ、所作や謡い・舞い・語り・を美しく表現するため極限まで洗練して様式化が行なわれた。また、原始的な喜劇が持つような、単に寿福を祝う祝言の笑いや、権力者を揶揄する風刺の笑い、さらには当代的な場当たりを狙った低俗・卑猥な笑いなどを超越して、観客の心を豊かにし、和み楽しませる明るい笑い、和楽の世界を体現するに至ったのである。
(3) 狂言の役割 ―「三番叟」のシャーマン性
現在の様々な演劇やお笑い(喜劇)の源流とも言われている狂言は、天下泰平を祈念する祝祷芸「翁」(おきな)の中で、古来より五穀豊穣を祈る「三番叟」(さんばそう)を勤めるという、もうひとつの重要な役割を担ってきた。すなわち、狂言師には、喜劇である狂言を演じることとは別に、祝祷曲「三番叟」を任され舞うという、二つの異った芸系が要求されるのである。ひとつの職能とは思えないこれらの異なる役割を狂言が担うことは、いったい何を意味しているのであろうか。
「三番叟」は、猿楽の源流を伝える儀式的要素が色濃い祝典曲で、その起源は我国古来の神事に遡ると考えられる。内容は、若者の勇壮な舞である「揉の段」と、老体での厳かな舞「鈴の段」の二部からなる。共に天下泰平・五穀豊穣を寿ぐものであるが、「揉の段」は、華やかに弾んだ囃子に始まり、「おおさえ、おおさえ、おお。喜びありや」と謡い出し、足拍子を踏みながら、明るく力強く舞うものであり、「鈴の段」では、黒式尉の面をつけ、鈴を振りながら寿福を祈り舞う。
この「三番叟」解釈については諸説あるが、一般的には、神格的で荘厳な白い翁にたいして、滑稽にそれを真似た肉体労働者階級の躍動的な黒い翁、白い翁のモドキ的要素であるともいわれている。両者はしばしば陰陽の関係に例えられる15)。また、面を掛けずに躍動的に舞う「揉の段」は若者が土地を開墾する姿であり、黒い尉面を掛け鈴を振る翁舞「鈴の段」は、村の長である長老が種を蒔いている、つまり農耕儀礼の舞踊化である等とも論じられてきた16)。しかし私は、白式尉面と黒式尉面、および「揉の段」と「鈴の段」の対照的な違いには、もっと深い意味があるのではないかと考えている。
原始的な社会において、芸能者はシャーマンであることが多い。狂言の源流である「猿楽」も「呪師」の流れを汲んでいる。「呪師」とは、神を招き、祈りを捧げるシャーマンのことにほかならない。シャーマンは見えないものと交信する力を持つ預言者でもあった。古来より預言者は神と交信するための特殊な儀式を行い、それが祭り事・芸能の根源となったのである。当然、シャーマンは一般的な人々とは考え方・身体的特徴など有様が異なる存在であり、それ故神秘性を兼ね備えていたのであろう。事実、現代まで伝わる狂言台本の中には、その名残と云える役柄が多数存在する。たとえば、「梟山伏」「蟹山伏」「茸」などに登場する山伏、「井杭」における「算置き」(陰陽師)、「石神」における巫女などである。
ところで現在、能楽の「式三番」では、女性は不浄の者とされ、「翁」「三番叟」を始め囃子方に至るまで、諸役を勤める者は最低でも前日、長くて三日から一週間女性と別火をして、精進潔斎をし、女性役の存在は勿論、当日は楽屋からも一切女性を排除して行われる仕来たりである。しかし、これは古来からの伝統であったのか、またその理由は如何なることであるか、なぜ現在の能楽における「式三番」に女は登場しないのか、全く明らかではない。
元来、神と交信できるのは、卑弥呼がそうであったように、新たな生命を宿す能力を持った女、なかでも最も神に近い女である「巫女」であり、古代からの神遊び・神事では、巫女が神を招き、下ろし、託宣を聞き、おもてなしをして、神を送る祭事を行っていた。その役目を男が取って代わった時に、また中世以降、女系から男系社会に変換が起きた時に、男が女に生る、変身するために仮面が用いられたのではないか。現に神事において、巫女は絶対に面を掛けることはない。それは、神に仕える巫女となった女は、仮面を掛けることによって神懸からずとも神を招き下すことができるからではないだろうか。
このように考えれば、「揉の段」と「鈴の段」に新しい解釈が成り立つであろう。つまり、「揉の段」の躍動はけっして若者による開墾を表すのではなく、一種のイニシエーションで、男が神懸かるための動作なのではないか。仮面を掛けると、視界は狭く、呼吸も楽ではない。「揉の段」で激しく動き回ったあとに仮面を掛けた狂言師は、肉体的にも精神的にも極限まで追い詰められる。ここに至って初めて、彼はトランスジェンダーし、巫女・シャーマンの資格を兼ね具え、続く「鈴の段」で、神を招き下ろすことができるのようになるのかもしれない。
能楽伝承の「翁」は、古来「式三番」と呼ばれているが、その由来はよくわかっていない。白式尉という白い翁面を掛ける荘厳な翁と、黒式尉という黒い翁面を掛ける躍動的な三番叟、それに直面で露払いを行う千歳の三体を表しているというのが定説であるが、露払いの千歳は本来含まれるべきではなく、一般には、能楽において退転してしまった「父之尉」と現代まで伝わる「翁」「三番叟」の三つで「式三番」とされる17)。
しかし、日本各地に伝わる民間芸能の「式三番」では、能楽で伝承が途絶えてしまった猿楽・田楽等の古体といえる「父之尉」や「延命冠者」等の祝?芸が現在も受け継がれている。そこでは、能楽の笑みを湛えた翁面とは異なり、眼が切れあがった、緊張しているような表情を持つ白い尉面を掛けた「父之尉」が祭司的役割を担い、童顔で笑みを湛えている面を掛けて稚児の姿を表した「延命冠者」を伴って、来訪した神を寿ぐ。老人と子供の取り合わせは万物の誕生と終焉を表しているのかもしれない。時には性別を変えて、延命冠者面は「若女」として、また黒式尉面は「媼」として現れる。中尊寺や毛越寺の「式三番」にも、「若女」と「老女」が含まれている18)。「媼」は黒く深い皺を額や頬に刻んだ面を掛け、大地を踏みならしながら結界を解いて舞う。ここに「三番叟」の動きの源流を見いだすこともできよう。能面以前の古い神事・祭式に用いられたとみなされている仮面を見ると、表情の両性具有性を感じることがある。「鈴の段」意味不明の様々な型があり、長らくそこに疑問を感じていたが、それらが皆女性的要素を表現しているのかもしれないと考えてみると妙に納得できるのである。
能楽は、中世より近世にかけて武家の庇護を受け、武士の式楽として諸藩の大名から扶持を受け、その芸形態を洗練させ、維新後の動乱をも潜り抜け現在まで一度も途絶えることなく伝承されている。しかし、現在われわれが知る能楽には発生当時の姿はほとんどないと言ってもよい。能楽は各時代を生き抜くために変遷を余儀なくされ、何度も形を変えながら芸脈を伝えてきたのだ。特に能楽がジャンルとして確立した中世後期は、絶対的存在であった天皇の権威が衰え、換わりに身分の低かった悪党・豪族達が台頭し、武家として権勢を振い始める時代であった。それは、アニミズム的古代原始宗教性、自然信仰が合理主義へ徐々に変わっていく転換期であったともいえよう。「式三番」も、「巫女」の本来的役割が、男系社会の新たな権威に姿を変え、現行の形へと変貌を遂げたのではあるまいか。
古来日本人は八百万の神を信仰していた。八百万とは無限大という意味であり、自分以外の全てを神と考え、感謝するという気持ちが根本にあったと考えられよう。また祖先信仰により、人間は死ぬと神になると信じられていた。そもそも自然環境の過酷な日本では、現代においても頻繁に地震、津波、台風など様々な災害を経験する。われわれの祖先たちは、自然の驚異や人間の無力さをつくづく痛感していたのであろう。そのために自然との共存共栄を第一として、生活を育んできたといえる。現に日本の神話を記した『古事記』では、人間たちのことを自然の一部である草木の如く例えている。祝祷芸「翁」の原型は古来の神招き祭式にあると考えられている。そこにおいて「三番叟」的な役割は、演者自らが神の依り代となり、神すなわち自然の全てである祖先霊を招き、感謝を伝え、見守って頂きたいと祈っていたのであろう。「三番叟」には、単なる農耕儀礼よりもさらに根源的な自然に対する畏敬の念、鎮魂興発の意が深く込められているのではないだろうか。
(4) 摩多羅神と仮面の両義性
2010年3月、島根県安来市の名刹・清水寺で、嘉暦4年(1329年)の胎内銘を持つ摩多羅神像と黒い翁面を含む8点の古面が発見された。摩多羅神とは仏教の護法神であり、様々な力を持つ謎の異神だが、とくに念仏と芸能の神でもある。延暦寺三世座主である慈覚大師・円仁が唐に留学した後、帰国する際に船中で虚空から摩多羅神の声が聞こえて感得し、比叡山に常行堂を建立して勧請し、常行三昧を始修して阿弥陀信仰を始めたとされている19)。また、恵心僧都・源信が念仏の守護神に勧請したともいわれており、念仏修行を邪魔しに来るテングを驚かし追い払うために、跳ね踊り、めちゃくちゃに経文を読む儀式を行なうなど、カーニバル的な芸能の場と結びついた神であった。体の奥底からわき出てくる踊るエネルギーがその本質であり、やがて猿楽の芸能神とされたのであろう20)。
摩多羅神は天台密教や民間信仰とも深くかかわるものであったが、特定グループの守護神であったため、信者を失ったときにあっさりと歴史の闇に姿を消してしまい、現在残っている摩多羅神の祭りは岩手・毛越寺の二十日夜祭などしかない。摩多羅神信仰の儀式についての記録はほとんど文献に残っていないが、その内容は秘密結社的であり、大変卑猥で背徳的な行為が行われていたらしい。つまり全てにおいての価値観の逆転・倒置であった。それこそが人間を超えた存在、神を表現する一番の方法だったのかもしれない。また、卑猥(性的)な表現は、本来、生命の誕生を示唆する神聖なものであった。
先述のように、「三番叟」の原型は「延年」や「呪師」の舞であるが、これはそもそも摩多羅神信仰が元であったともいわれている。「摩多羅神」とは様々な力を持つ謎の異神だが、古来中国の道祖神であったらしい。それが日本の祖先信仰と習合して生死を司る来訪神となったり、外道・邪鬼を祓う荒神としての性格を持つようになったと考えられる。
「三番叟」には、「死と蘇り」、「復活と蘇生」を表現する側面もあると思われる。毛越寺に残る「延年の舞」は、能楽「三番叟」で使用する黒式尉面に似た黒い面を付けるが、終始腰を直角に曲げて百歳の老婆が腰を屈めて舞う「老女舞」と呼び伝承されている。ここにも、しい生命を司ることができる女性の神秘性・巫女的要素が伝えられている気がする。古来神とは性別を超えた存在で、両性具有的特徴を持つ。人間のように男女が明確に区別されていることは、実は神から最も遠い存在であるということなのかもしれない。
摩多羅神像と古面が発見された安来市清水寺では、2013年4月に御堂の落慶法要が行われた。このとき「摩多羅神の舞」が復元されることになり、私は復元舞の型附けに携わる機会を得た。東日本大震災や世界各地で起きている大規模な自然災害に直面して、産業革命以降、資本主義経済の名の下に環境破壊を繰返し自然への感謝畏敬の念を忘れてしまった人間達の奢りに対する、自然からの警鐘と感じた私は、今こそ「三番叟」の持つ本来的意義を考えていたが、民俗仮面研究家・乾武俊氏と共に、この復元舞を翁の舞ではなく媼の舞として考証創作することにした。また伴奏は笛一管として能楽師笛方森田流・槻宅聡氏のご協力を得て、鎮魂延年の舞「黒い媼舞」が生まれたのである。清水寺落成法要における上演時には、芸能の原点として摩多羅神につながる荒神信仰に立ち戻り、「鎮魂延年の舞」として地鎮・鎮魂の心にて舞った。

図1:創作復元「摩多羅神」媼の舞
この際に使用した面も、私が関わって復元したものである。同寺で発見された古面は猿楽成立以前のものであるが、大変損傷が激しく、使用不可能なため、その複製を能楽面彫刻家の松村満忠氏・植田美雲氏御両名にお願い致し、大変崇高な面が現代に蘇ったのである。古面の復元にあたり私が強く感じたのは、面の持つ両義性であった。
「摩多羅神の舞」の流れをくむ「翁」では、現在シテ方が白式尉面を着面して「翁」役を勤め、狂言方が黒式尉面を付け「三番叟」役を勤める。また一度退転してしまい滅多に上演されることがない父之尉・延命冠者では、父之尉面や延命冠者面といった男面のみにて構成されている。しかし、岩手県毛越寺の摩多羅神舞は若女舞と老女舞であり、清水寺の古面も老女面のように思えた。素晴らしい面は様々な表情を持つのは周知の事であるが、表情は心の現れであり、その心が豊かであるのは人知を超えた神の領域であろう。
それでは神の領域とは一体何か。日本の祖先信仰では、神は父であり母なのではないか。面には父性と母性の両方を兼ね備えている必要があるのではないか。生命の誕生と死。太陽と大地。陰と陽。これが仮面の両義性であると私は考える。
(5) 芸能者の変遷と狂言の未来
第3節で述べたように、古代の芸能者は「喜劇」と「シャーマン」二つの根幹的要素を一同に兼ね備えていたが、武士が台頭する中世(14世紀頃)より後醍醐天皇の建武の新政が事実上崩壊し、天皇の権威が失墜するに従って、神と交信できた芸能者達は、その地位を奪われ、超人から非人へと転落せしめられ、蔑視され始める。いっぽう狂言は、遂には武家式楽に定められ、武家社会に同化し合理管理社会に適応していく。
天皇に代わって武家が支配する時代が到来すると、芸能者の「シャーマン」的要素は徐々に排除され、滑稽な俳優は賎視されるようになる。新たな支配者である武士に抱えられることを選んだ「猿楽」(狂言の母体)は、「シャーマン」的要素を武士好みの内容に巧みに書き換え、幽玄美を強調する能と、風刺性を封印し俳優的要素のみが受継がれた狂言に二分したのである。ただ、その古体である「三番叟」には、シャーマン性の痕跡が色濃く残っているのである。
現在まで約650年間一度も途絶えることなく伝承されている能楽は、その長い時間をかけ洗練・熟成されてきた。特に狂言の笑いは、神への祝福、和み楽しむ「和楽」の世界に昇華され、非常に高い芸術性を備えている。しかし、その反面、武家式楽や近代欧米合理主義の影響により、古代原始宗教色から近代合理主義への思想転換や、演劇性・音楽性・舞踊的要素の重視等、技術主義に傾き、その根源的意義を見失ってしまったように思う。
「猿楽」が江戸期に武家式楽となってその牙を抜かれた後、歌舞伎が一時その役割を担うが、現在ではこれも伝統芸能化し、洗練されてしまった。芸能による社会批判は明治期の講談、自由民権運動、壮士芝居、バイオリン演歌、アングラを最後に現在は消滅してしまったのではないか。日本の芸能には、社会に対するメッセージ性が希薄になりつつある。
自然の摂理を無視して、観念による生活が営まれる社会となり、人間が自然を支配しようと考えるにつれて、本来の「シャーマン」達が排除された時代となってしまった。現代社会が抱える問題の解決には、見えないものを感じて敬い祈ることしか方法はないかもしれない。その意味で、自然環境が厳しい故に自然信仰が現在も色濃く残っている日本が、混迷する現代世界に果たす役割は大きいと云えるであろう。
残念ながら、現在日本の喜劇には「狂言」に限らず、混迷する社会に対するメッセージが欠落していると言える。芸術的洗練だけではなく、社会に対する風刺・報告がなされなければ、芸能としての本来の意義を果たすことができないであろう。近代芸術はあまりにも自然から掛け離れてしまったのではないか。祈りを忘れてしまったのではなかろうか。狂言が本来持っていたメッセージを単なる社会批判ではなく、人間のあるべき姿や根源を見つめ直す鍵となるべく再構築することが、「狂言の源流を探る」本プロジェクトの真の狙いだと私は考えている。
(小笠原匡)
注
| 1) | 高田和文「コンメディア・デッラルテと狂言―東西の笑いの交流」『静岡文化芸術大学研究紀要』第1巻、2000年、pp.29-36 ; Gary G. WHITE, ‘Contrast in Comedies : Japanese Kyogen and Italian Commedia dell’Arte’ 『岐阜聖徳学園大学短期大学部紀要』第36号、2006年、pp.79-107 ; 2004年と2005年に福岡、京都、大阪、東京で行なわれた「Roma Kyogen 来日公演」およびそれに伴うシンポジウム ; 2007年にイタリア文化会館東京で開催された「狂言とコンメディア・デッラルテ国際フォラム」など。 |
| 2) | 松尾恒一『延年の芸能史的研究』岩田書院、1997年 ; 表章・天野文雄『岩波講座 能・狂言<1> 能楽の歴史』岩波書店、1987年、pp.11—20:松尾恒一『儀礼から芸能へ 狂騒・憑依・道化』角川学芸出版、2011年、pp.18-19 |
| 3) | 狂言「盆山」等をもとにした 「TONTO盗人」作( 2009年12月、山本能楽堂); 狂言「鎌腹」をもとにした「はらきれず」および「蚊相撲」をもとにした「異人相撲発気揚々」(2011年2月、大阪能楽堂)。いずれも作・構成・演出は小笠原匡。・アンジェロ・多木陽介 |
| 4) | 共演は日本国内や海外において数多く行なわれてきたが、本プロジェクトと同様に両者のコラボレーションによる翻案狂言の試みとして、シェイクスピア研究者の関根勝氏の取り組みを挙げることができる(http://project-si.art.coocan.jp/aboyt.html)。 |
| 5) | 2012年9月1日、堺能楽会館。 |
| 6) | 2012年9月2日、大阪ドーンセンター。 |
| 7) | 2012年10月15~17日、ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学Auditorium Santa Margherita。 |
| 8) | 2014年3月3~4日、ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学Auditorium Santa Margherita。 |
| 9) | 2014年10月27~29日、ボローニャ大学Laboratori delle Arti。 |
| 10) | 2015年3月13~15日、阪急うめだホール。 |
| 11) | 2006年12月、山本能楽堂 |
| 12) | 2008年2月、山本能楽堂 |
| 13) | 2009年3月、山本能楽堂 |
| 14) | 例えば、田舎の召使いアルレッキーノはベルガモ方言、裕福な商人パンタローネはヴェネィア方言、博識を鼻にかけているドット―レはボローニャ方言というように、言葉遣いそのものが登場人物の特徴を示す。 |
| 15) | 原田香織『能狂言の文化史 室町の夢』世界思想社、2009年、pp.26-27。 |
| 16) | 同書、p.31。 |
| 17) | 表章・天野文雄、前掲書、pp.20-22;新井恒易『恍惚と笑いの芸術[猿楽]』新読書社、1993年、p.54。 |
| 18) | 乾武俊『能面以前 その基層への帰還』私家版、2012年、p.221。 |
| 19) | 「渓嵐拾葉集」大正新情大蔵経・巻七十六・統諸宗部七,第三十九常行堂摩多羅神事 |
| 20) | 「望月大仏教辞典」「広隆寺大略縁起」 |
| 21) | 山本ひろ子『異神 中世日本の秘教的世界』平凡社、1998年、pp.110-113。 |